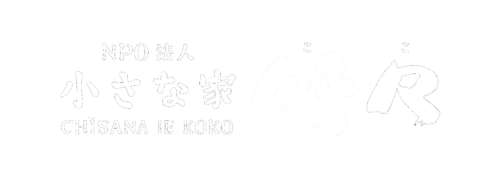「ヤングケアラー」という言葉を最近よく耳にします。みなさんはその内容をご存知ですか?
法的には
家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者
を指し、国・地方公共団体等が支援に努めるべき対象とされています。
でも、家族の外からは見えづらいため、一人苦しんでいる子ども・若者が多いんですよね。
「ケアする」という点で同じ立場にある者として、私たちにも何か出来ることはないだろうか?
そこで!まずは「ヤングケアラー」についての基本的な知識を、私たちだけでなく広く地域の方々と共に学ぼうと思い立ちました。
8月6日(土)春日市社会福祉協議会にて、研修会「ヤングケアラーについて」を開催。
講師は、福岡市子ども家庭支援センター「SOS子どもの村」センター長・松﨑佳子さんです。

市長、副市長をはじめ、教育長、子育て支援課、そして児童民生委員さんなど、40名近くの方々に来ていただきました。


松﨑さんのお話はとても分かりやすく、また参加者のみなさんからは、「グループワークでいろんな方のお話を聞けたのも、大変良かった」などの感想をいただきました。
この研修で、子どもの権利やヤングケアラーの定義、ヤングケアラー本人が“自分が困っていることに気づいていない”ことなど、今の実態を知ることができました。
まずは、本人が声を上げやすい環境づくりと周りの“気づき”、そしてその声をどこに持っていくか?
行政と関係機関との連携づくりが必要です。
その中で小さな家処々が何ができるか?考えさせられる一日でした。
小さな家処々は、これまで認知症についての学習会は数多く実施してきましたが、それ以外の分野にはなかなか目を向けることができませんでした。ヤングケアラーについて今後も考えていくとともに、少しずつ視野を広げていくことも大事だな、と思いました。
福岡市子ども家庭支援センター「SOS子どもの村」
“すべての子どもに愛ある家庭を”をミッションにかかげ、2010年4月、福岡市西区今津に開村されました。
5棟の建物があり、2棟はショートステイ専門で、子どもたちを短期間、一時的に預かるスペース、残りの3棟は里親と子どもたちが一緒になって生活できる場所です。